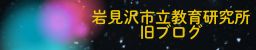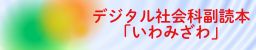第1回「教頭・研究担当者研究協議会」が開催されました
岩見沢市では、「確かな学力の向上」を重点に掲げ、①授業時数特例校制度の活用 ②学校として統一性・一貫性のある校内研修の推進 ③コミュニティ・エリアにおける9カ年を見通した組織的な学力向上 ④学習集団づくりにつながる「岩見沢型ピア・サポート」の推進について各学校に具体的な取組を求めています。

これらの取組の推進に向け、市内各学校の教頭、研究担当者が一堂に会して年4回、本研究協議会が実施されます。今年度は「学習者主体による授業づくり」に向けて、市内全22校が、ねらい、めざす所を共有し、各学校が知恵をしぼり研究・研修をすすめていくことが期待されています。

また、「令和の日本型学校教育」の構築の中で重要とされている「研修観の転換」を図るためにも、各学校の管理職、校内の研究・研修をリードする担当者を集めての本研究協議の役割は大きなものがあると思います。先生方の課題に対する問題意識の醸成と問題意識に基づく主体的かつ協働的な協議が求められます。
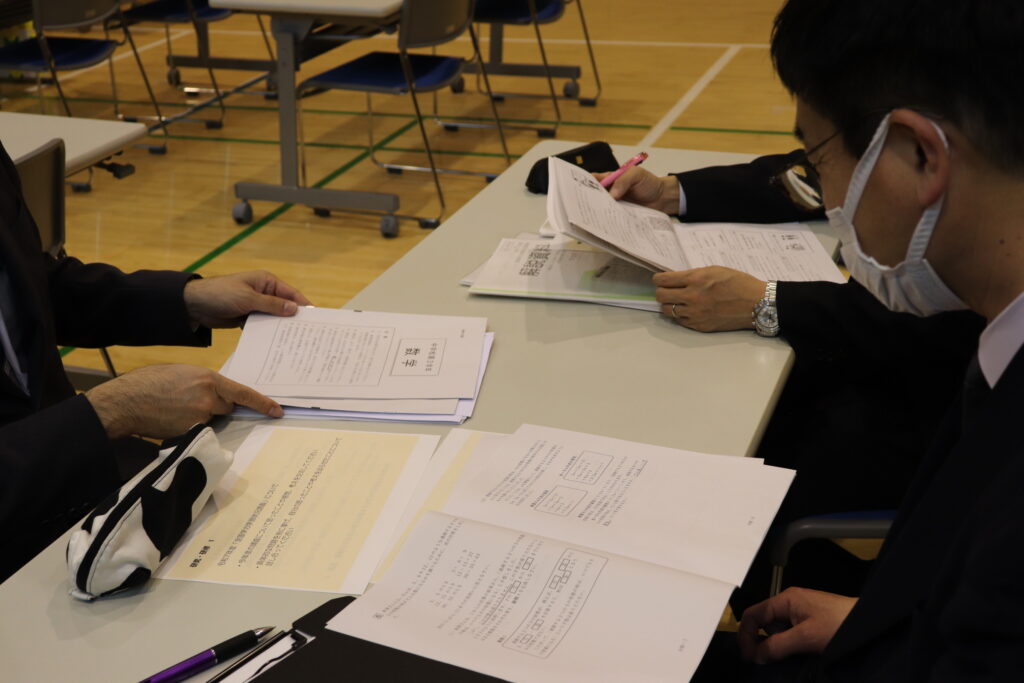
今回の研究協議では、直近に実施された、全国学力・学習状況調査について、具体的な各教科の問題を協議することで、子どもたちに求められる力、そのための各学校の取組について考えてもらいました。

出席された先生からの振り返りからは、
「今回の協議会では全国学力・学習状況調査について中学校の先生のお考えも聞けたことが有意義でした。9年間を見通した学びの連続性を十分意識した学習指導の必要性を強く実感しました。」

「読解力の重要性。その力をつけるためには、国語の授業だけなく各教科等、学校の活動全般で行うことが大切である。」
「Bグループでは、学力調査の問題で、自校と他校で正答率が低い問題、高い問題を比較し、何が弱いかを話し合いました。テストの内容は難しくなかったため、国語の読解力や日常とのつながりを意識していく必要があるということを指摘する声が多かったです。また、コミュニティ・エリアでピア·サポートの取り組みが強化されており、中学校に上がる上で、同じところを目指していくことや接続会議にも生かしていくことを確認しました。」

「1つ目の協議の全国学調の感想交流について。出題された問題の傾向から、どんな学習が必要なのかの意見交換を柱に行いました。基礎・基本の定着はもちろんなのですが、生活に即した問題が多く、実体験・経験があるかどうかで差があるかもしれないという話から、総合的な学習の時間の重要性をあらためて確認しました。また2つ目の協議の今年度の研究の交流では、大筋同じ考えの下で研究が進められていくことが確認できました。」
「昨年度のグループとは違い、同じ中学校区で学調分析の話ができたことが、大変有意義な時間であった。正答率の低かった問題や無回答率の高い問題を交流したことで、同じ地域の児童が抱えている課題にグッと迫ることができました。」

などの振り返りがみられ、子どもたちに求められる力やこれからの取組への中学校区エリアでの共有ができたと思います。